この記事の監修者
-

-
フランスベッド
メディカル営業推進課
課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、
社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、
可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー
家族が認知症になったときにどのように対応したらいいのか、症状や対応方法についてご紹介します。
2025年7月30日
認知症とは、病気などによって記憶や思考、判断などの認知機能が低下している状態を指します。脳の細胞が損傷を受け、機能が著しく低下するため、日常生活に大きな支障をきたす状態になります。病気の進行に伴って、物忘れだけでなく時間や場所までわからなくなったり、性格が変わったり、感情のコントロールが難しくなるといった多様な症状が現れることもあります。
認知症は誰にでも起こりうる病気で、高齢化が進む日本において患者数は増加傾向にあります。厚生労働省の発表によると、2040年には認知症患者が584万人を超えると推計され、国民の約6.7人に1人が認知症になると言われています。
家族や近親者、知り合いなどが認知症になった場合にどのように接したら良いのかは大変デリケートな問題です。
認知症は認知機能が低下する症状ですが、行動を起こすまでに考える時間が必要になってしまい、結果として常に動作がゆっくりになりがちです。認知症の方と接する際は、「急がせない」、「驚かせない」、「自尊心を傷つけない」の3つを常に考慮してください。認知症の方の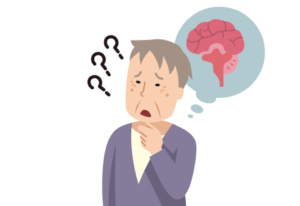 立場を思いやり、気持ちに寄り添いながらサポートすることが望ましいです。接し方次第で症状が落ち着くこともありますし、逆に悪化することも考えられます。認知症のご本人も不安な気持ちを抱くため、決して無理強いをせず、さりげなく受診を促してみましょう。ご家族の心配も計り知れないので、決して抱え込まずに専門機関などに相談することをおすすめします。
立場を思いやり、気持ちに寄り添いながらサポートすることが望ましいです。接し方次第で症状が落ち着くこともありますし、逆に悪化することも考えられます。認知症のご本人も不安な気持ちを抱くため、決して無理強いをせず、さりげなく受診を促してみましょう。ご家族の心配も計り知れないので、決して抱え込まずに専門機関などに相談することをおすすめします。
認知症の方は、何かを考えて行動を起こすまでにどうしても時間がかかります。周囲がご本人を急がせるのは心にプレッシャーをかけることになり、逆効果になります。慌てずにゆっくり考えれば、やれることも多くありますので遅いからといって急かさないようにしましょう。
驚かせないことも大切です。認知症の方の場合、驚かせるとパニックを起こしやすい傾向があるので、本人のペースを乱さないように注意が必要です。できる限り、ご本人の視界に映る正面から話しかけるなど驚かせないようにしましょう。
自尊心を傷つけないことも大切です。例えば、「こんなこともできないの!」「勝手にやらないで!」などと言ってダメ出しをすると、自尊心を傷つけ、感情にしこり残し心を閉ざすこともあります。このようなことでさらに症状が進行する場合もありますので気をつけましょう。
認知症の方は、事実や体験は忘れても、そのときの気持ちや感情はしっかり記憶しているといわれています。例えば家族から注意されたり叱られたりした場合、実際のやり取りや事実関係は忘れていても、怒られて嫌だったというネガティブな感情は長く残ってしまいます。認知症の方への対応でやってはいけいない9つのことを紹介しますので参考にしてください。
叱られた原因を理解できず、叱られた時のネガティブな感情だけが残ってしまうので、叱ることには気をつけてください。叱るようなことがあった場合でもすぐに叱るのではなく、行動の背景などを考えるなど間をあけて冷静さを持つようしてください。
強制して認知症の方が好まないことや嫌がっていることをさせるとご本人に大きなストレスがかかります。認知症の状態でも、感情面は常に作用していしますし、何より無理強いはご本人のプライドを傷つけるので、はじめから避けるようにしてください。
「今これして!」「あれやって!」と命令するのも、認知症の方の自尊心を傷つける原因となります。時間の余裕がなく、寛容な気持ちが欠けているとつい命令口調になってしまいますが、マイナスの感情を抱かせると反発されやすくなりますので気をつけてください。
ご本人の行動を過剰に制限してしまうのも良くないです。できることまで制限すると、精神的な苦痛につながりやすくなりますので、なるべくできることは周囲がサポートをして行い自信を持ってもらえるようにしましょう。反対に、危険の高い自動車の運転などは、きちんと話をして制限に納得してもらう必要があります。
役割を取り上げることも良くないです。認知症だからといって、すべてのことができないわけではありませんので役割を取り上げてしまうと、やりがいや楽しみまで奪ってしまうことになりかねません。精神的苦痛からうつ状態を招くリスクもあるため可能な範囲で家事や仕事、趣味などの活動の場を作ってあげるようにしましょう。
認知症の進行につれて、子どもがえりをすることもありますが子ども扱いはやめてください。あくまでも敬意を持ち、大人として接するように心がけないと、自尊心を傷つけると感情的になり、周囲のサポートを受け付けなくなる可能性もありますので気をつけてください。
何もさせないことも良くないです。危ないからといって本人ができることまですべて周囲が代わりに行うと、自分の存在価値を見失ってしまう恐れもあり、それによって認知症進行のリスクを高める可能性もありますので注意が必要です。
大きな声を出さないようにすることも大切です。認知症の方に大きな声を出すと、不安な気持ちから相手に対して恐怖心を抱いてしまいます。ご本人には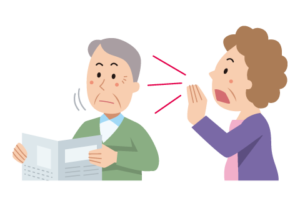 原因や状況の判断がつかないため、大声を出す人は「怖い人」だと勘違いをし、警戒されるますのでできるだけ優しい声で話かけるようにしてください。
原因や状況の判断がつかないため、大声を出す人は「怖い人」だと勘違いをし、警戒されるますのでできるだけ優しい声で話かけるようにしてください。
ご本人が何かミスや失敗をしても、細かく指摘しないようにしましょう。例え大きな間違いだったとしても、ご本人は正しいと信じているので、まずは受け入れてあげるようにしてください。むやみに指摘を繰り返すと、ご本人は何が正しいのかがわからなくなりパニック状態に陥りやすいので気をつけてください。
認知症の方に何気なく言ってしまった言葉であっても気持ちを傷つけたりペースを乱したりしてしまうことがあります。「否定する言葉」、「責める言葉」、「急かす言葉」の3つはご本人に言ってはいけない言葉ですので認知症の方と接する際には極力避けるようにしてください。

認知症の方が話す内容に対して、最初から否定する言葉を使うのは良くないです。例えば、認知症の初期症状として記憶障害が現れる場合が多いですが、このような時に本人へ物忘れについて直接指摘しないようにするのが基本です。ご本人が覚えていることや信じていると思っていることを否定してしまうと、ご本人が戸惑うばかりでなく、怒りを感じて孤立してしまう恐れもあります。食事直後なのに「まだ食事をしていない」と訴えたり、すでに引退した仕事を「まだ現役で働いている」と信じ込んでいたりする場合、あえて否定はせずに、ご本人に寄り添った言葉をかけてあげましょう。
責める言葉も認知症の方に使ってはいけない言葉です。もし言動が普通でなかったり、物事がうまくできていなかったりしても、できないことを「なぜできない?」と問い詰めたり、ありもしないことを「嘘でしょう?」と疑ったりするのもNGです。認知症の症状の一つに「物盗られ妄想」がありますが、「どこかで落としたんじゃない?」「勘違いでしょ?」などの返答は避けてください。決してご本人が間違っていることを責めない言動を心がけ、「今から一緒に探してみよう!」とサポートする姿勢をご本人に伝える、あえて別の話にすり替えるなどの対応が良いでしょう。
急かす言葉もNGです。認知症の方が自分のペースでゆっくりやっていることに、周囲がイライラして急かす言葉をかけるのは絶対に避けましょう。例えば、食事の際やトイレに入っている時など、時間がかかっていて待ちきれずに「早くして!」「もっと急いで!」などと不用意に言葉をかけるとご本人のペースが乱れ、気持ちを萎縮させたり、不満を抱かせたりすることになります。できる限り、「今困っていない?」「手伝いは必要?」などと尋ねるようするなど気遣う姿勢を維持しましょう。
周囲の人が慌てず焦らずに、ご本人の気持ちに寄り添ってサポートする姿勢が最も効果的です。
―認知症高齢者の接し方について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「認知症の方との接し方のポイントは?話し方の基本や具体例をシーン別に解説」
認知症の方とのかかわり方は、ご本人の尊厳を保ち、安心して生活を送っていただくためにも非常に重要です。かかわり方のポイントをご紹介しますので、認知症の方の状態を理解して、不安を和らげる接し方を心がけてください。
認知症の方に対して共感の気持ちを持つようにしましょう。
認知症の方は、記憶や状況認識に困難を抱えることがあります。その結果、事実と異なる内容を話したり感情的になったりすることもありますが、「そう思っているのですね」「大変でしたね」など、ご本人の感情を受け止める言葉をかけましょう。否定せず受け入れることでスムーズに安心感を促し、心を開きやすくなるはずです。ご本人が混乱している時や不安を感じている時に寄り添う姿勢を見せることは、信頼関係を築いて穏やかな気持ちを保つ上で非常に重要となります。
認知症の方とペースを合わせることも大切です。
認知症の方は、何かを理解したり行動に移したりするのに時間がかかることもありますが、焦らせたり急かしたりすると大きなストレスとなり、混乱や不安を招く原因になります。会話のスピードや行動のペースを相手と合わせることを意識し、ゆっくりと穏やかに接しましょう。ご本人が納得するまで待つ姿勢も大切です。例えば、食事や着替えの際も無理に急がせないで、様子をよく見ながら必要な手助けをさりげなく行いましょう。余裕を持った対応こそが、ご本人の安心につながります。
短く具体的な言葉で説明するようにしましょう。
認知機能が低下している方は、複雑な指示や抽象的な表現は理解しにくい場合があります。話す際は、「〇〇しましょう」「△△を取ってください」など、一度に伝える情報を少なくして、短くわかりやすく具体的な言葉を選ぶように心がけましょう。ジェスチャーを交えたり、実物を見せたりするのも有効です。例えば、「そろそろお風呂に入りましょうか」ではなく、浴室を指さして「お風呂に行きましょう」と端的に伝えられるとより理解しやすくなります。
笑顔で明るく接することも大切です。
認知症の方は、言葉の内容だけでなく表情や声のトーンから相手の感情を読み取る傾向があります。不安な気持ちをできる限り抱かせないためにも、常に笑顔で明るく接することを意識してください。優しい声や穏やかな表情を意識して話しかければ、ご本人は安心感を抱いて良好なコミュニケーションを築きやすくなるはずです。特に、混乱している時や戸惑っている時にこそ、あなたの温かい表情や声が何よりも大きな安心材料となるでしょう。
話を丁寧に聞くようにしましょう。
認知症の方が話す内容は、時に話が飛んだり、辻褄が合わなかったりすることもあります。そんな時にも、途中で遮ったり訂正したりするのではなく、最後まで丁寧に耳を傾けるようにしましょう。ご本人の意思を汲み取ろうと誠実に努め、相槌を打つ・うなずくなど工夫することで「話を聞いてもらえている」と感じ、安心でしてもらえるでしょう。事実と異なる内容であったとしても、ご本人の気持ちを受け止めて穏やかに耳を傾けることで、混乱や不安を軽減できます。
スキンシップをとるようにしましょう。
言葉でのコミュニケーションが難しくなってきた場合でも、スキンシップが有効なコミュニケーション手段となり得ます。手を握る、肩を優しくたたく、背中をさするなどの非言語的なコミュニケーションは、ご本人の気持ちを落ち着かせて安心感を与えます。認知症の方が不安な表情を見せていると感じたら、優しく手を握るだけで気持ちが落ち着くこともあるので日頃からぜひ意識をしてみてください。ただし、ご本人が嫌がる場合は無理に行わないようにしましょう。
認知症の介護は、ご本人だけでなく介護する家族にとっても大きな負担となることがあります。家族が介護をするにあたって押さえておくポイントをご紹介しますので、無理なく介護を継続し、心身の健康を保ち、介護疲れを予防するための参考にしてください。
認知症の方に安全な環境を作ってください。
認知症の症状が進むと、危険を認識する能力が低下して思わぬ事故につながることがあります。例えば、誤飲の危険があるものは手の届かない場所に保管するなどの対策が必要です。他にも転倒防止のために段差をなくす、火災や水害を防ぐためにガスや水道の元栓を確認しやすくする、徘徊を防ぐために施錠を強化するなど、ご本人が安全に過ごせる環境を整えましょう。
認知症の方の個性を尊重してください。
認知症になっても、その方の個性や好みは変わりません。以前好きだったことや得意だったことを可能な範囲で続けられるようサポートしましょう。無理に何かをさせず、ご本人の意思を尊重してできることを増やしていく関わり方を心がけてください。例えば料理が好きだった方には簡単な手伝いを頼むなど、ご本人のできることを応援し、自己肯定感を保つ取り組み方がベストです。
外部のサポートを活用してください。
認知症の介護は、一人で抱え込まずに地域包括支援センターや介護保険サービス、家族会など、様々な支援機関やサービスなど外部のサポートを積極的に活用しましょう。専門家の力を借りれば介護の負担が軽減し、ご本人にとってもより良い生活を送れるようになるはずです。また、専門的な知識や情報に触れて介護の質が向上すると、心のゆとりにもつながります。
周囲と比較しないようにしてください。
認知症の進行は人それぞれ異なります。同じ病気でも症状の出方や進行度合いは様々なので、他の認知症の方や、認知症になる前の状態とご本人を比較しないようにしましょう。ご本人の今の状態を理解して、その時々に合わせたサポートを行うことが重要です。過去と比べるのではなく、今できることに目を向けて小さな変化や成功を喜ぶようにしましょう。
行動の背景や理由を探るようにしてください。
認知症の方が一見理解しがたい行動をとる場合でも、そこには何かしらの背景や理由があることが多いです。落ち着かない様子であれば痛みや不快感があったり、感情的になったりしている場合は不安やストレスがあるなど行動の裏には理由があります。その理由を推測し、それを取り除くための対応を心がけましょう。ご本人の行動を注意深く観察するうちに、言葉にならないサインを読み取れるようになるのが理想的です。
認知症の方と接するときは、責めたり叱ったりせず、落ち着いて対応することが大切です。ここでは、シチュエーション別に対応するときのポイントをご紹介しましょう。
ただ大声を出しているわけではなく、何か理由があるはずですから、冷静に対応しながらその原因を探ってみましょう。攻撃的な態度が見られる場合は、落ち着くまで少し距離をとって見守るか、別の人に交代してもらいましょう。
他のことに気をそらし、得意な手仕事を頼むなどすると、外へ出ようとしていた理由を忘れて落ち着くことがあります。本人の話を否定せず、もうすぐお迎えの車が来るのでお茶でも飲んで待ちましょう、外は冷えるので上着でも着ましょうか、などと別の行為につなげて落ち着くのを待ってみましょう。
本人の気持ちを受け止め、一緒に探しましょう。探し物を家族が手渡すと盗まれたという疑念が残ることもあるので、なるべく本人の手で発見できるように誘導するとよいでしょう。
―妄想について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「認知症の妄想(作り話)とは?症状の特徴や原因、対応方法まで解説」
今から用意しますからもう少し待ってくださいね、と言って少し時間を空け、忘れてもらうのもひとつの方法です。お腹にたまらないような軽いデザートを提供するのもよいでしょう。
羞恥心を和らげるように落ち着いた態度で接することが大切です。トイレの場所がすぐわかるように貼り紙をする、早めにトイレへ誘導するなど、失敗の回数を減らす対策も考えましょう。
―排泄介助について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「排泄介助の正しい方法とは?適切な排泄方法の手順とポイントについて解説」
汚れる範囲を最小限にするためにも、まずは手をきれいに拭き取り、その後にお風呂へ誘導して汚れをきれいに洗い流します。介護する方にとっては大きな負担ですが、感情的にならず穏やかに対応することを心がけましょう。壁に保護シートを貼る、 ベッド周りに防水シートを敷くなど、掃除しやすい環境にして、後始末の負担を減らす工夫をしておくとよいでしょう。
ベッド周りに防水シートを敷くなど、掃除しやすい環境にして、後始末の負担を減らす工夫をしておくとよいでしょう。
―弄便について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―
▶ 「弄便(ろうべん)はなぜ起きてしまうの?原因と対策を解説」
徘徊などで行方不明になってしまったときは、すぐに周囲の協力を求めることが必要です。家族や近所の方で確認が取れない場合は、警察、ケアマネジャー・地域包括支援センター、自治体などへ至急連絡しましょう。軽度の認知症でも自力で帰宅できず行方不明になる場合がありますので、無事に保護するまでの時間を最短にすることが大切です。日頃から冷静に対応できるよう、ある日突然行方不明になり得ると想定し事前準備をしておきましょう。
【対策例】
・家内でもセンサー類や徘徊防止かぎ等を使用 (過剰な行動制限は禁物)
・外出時、GPS機や氏名・連絡先を記載したタグを利用
・近所の人や警察に徘徊情報の提供を事前に依頼
・ケアマネジャー、役所の担当、かかりつけの医療機関や主治医などに普段から相談
認知症について気になることや困ったときに以下のサイトも参考にしてみてください。
■認知症の症状について細かく説明を知ることができます。
厚生労働省 政策レポート 認知症を理解する
■厚生労働省が行う認知症施策について紹介されています。
厚生労働省 認知症施策
■厚生労働省 認知症に関する相談先の一覧が紹介されています。
厚生労働省 認知症に関する相談先
■家族や自分が認知症になったときのために知っておきたいことを紹介しています。
「政府広報オンライン知っておきたい認知症の基本」
■家族が認知症でないかと心配している方へのアドバイス。
公益社団法人認知症の人と家族の会 家族が「認知症ではないか」と心配しているあなたへ | 認知症を知る |
■認知症について幅広く紹介しています。
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 「こころの情報サイト」
認知症になると、理解しがたい行動をとることもありますが、本人にとっては何かしらの理由があってのことです。感情的にならず、本人の気持ちに寄り添いながら、落ち着いて対応することを心がけましょう。認知症介護は、身体的にも精神的にも負担が大きくなります。必ず介護を一人で抱え込まず、周囲の方に協力してもらう、介護サービスを活用するなど、自分自身も大切にしてください。
フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。

商品やサービスに関するご質問、
ご相談にお答えしています。

商品やサービスに関するご質問、
ご相談にお答えしています。

まずはお気軽に資料請求を。
無料カタログをご送付致します。